引用元: Wikipedia
「科挙の難易度」について検索しているあなたは、その試験がどれほど過酷だったのか、具体的な情報を探しているのではないでしょうか。
科挙とは何か、その基本的な知識から、驚異的な倍率や膨大な暗記量が求められた試験内容、そして実際の試験問題に至るまで、多くの疑問をお持ちかもしれません。
この記事では、科挙の過酷さを示す衝撃的なエピソードや、追い詰められた受験生によるカンニングの実態、さらにはプレッシャーで発狂する者までいたという事実を掘り下げていきます。
また、現代の試験との比較や、そもそもなぜ日本に科挙がなかったのかという歴史的な背景、そしてネット掲示板のなんjなどで今なお語られる科挙のヤバさについても、客観的な情報に基づいて解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたが抱いていた科挙に関する様々な疑問が解消され、その歴史的な意義と異常なまでの難しさについて深く理解できるはずです。
- 科挙の具体的な試験内容とその過酷さ
- 合格率の低さや壮絶なエピソード
- カンニングや精神崩壊などの試験の実態
- 現代の試験との比較や日本で導入されなかった背景
科挙の難易度は想像を絶するレベルだった
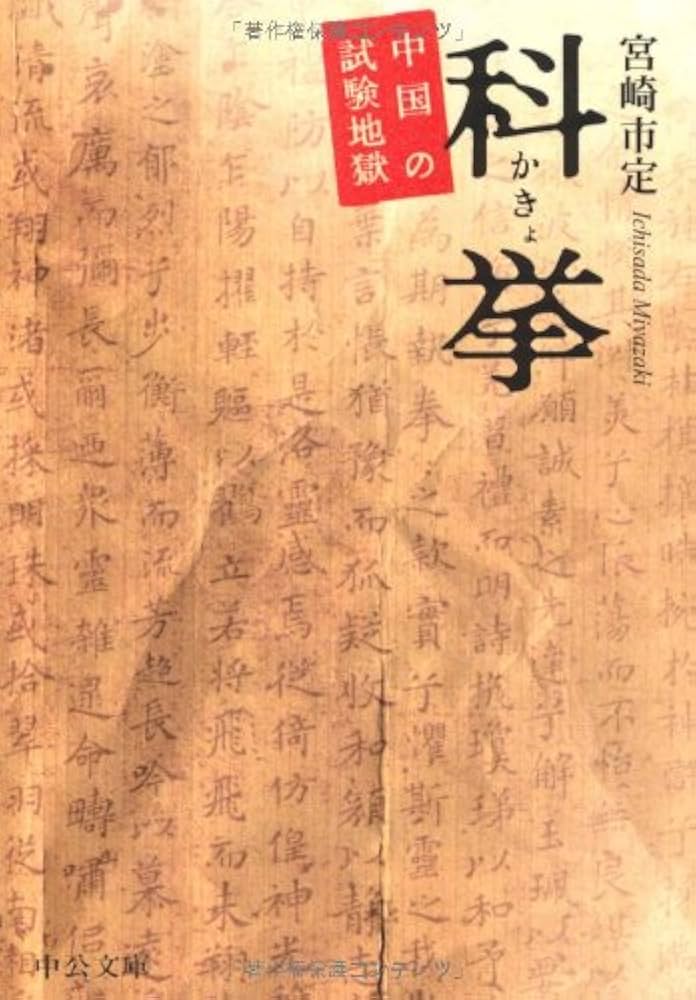
引用元: amazon
このセクションでは、科挙という試験制度の概要から、その難易度を構成する具体的な要素までを掘り下げていきます。
試験の基本的な仕組みや求められた知識量、そして驚くべき合格率など、科挙の過酷さを理解するための基礎知識を解説します。
- まずは科挙とは何かをわかりやすく解説
- 科挙の試験内容と驚きの問題形式
- 膨大な暗記量が求められた儒教の経典
- 合格率が低すぎる驚異の倍率とは
- 科挙の壮絶さを示す有名なエピソード
まずは科挙とは何かをわかりやすく解説

moya lab イメージ
科挙とは、主に中国の歴代王朝で約1300年間にわたって実施された、官僚を選抜するための登用試験制度のことです。
この制度の最大の特徴は、家柄や身分、財産に関わらず、学力さえあれば誰でも高級官僚になれる可能性が開かれていた点にあります。
このため、多くの人々にとって科挙の合格は、一族の名誉を高め、貧困から抜け出すための唯一と言ってもよい道でした。
隋の時代に始まり、清の時代末期である1905年に廃止されるまで、国家の運営を担う人材を選び出す根幹として機能し続けたのです。
言ってしまえば、個人の能力のみを評価基準とするこの制度は、当時の社会において非常に画期的なものでした。
しかし、その門戸が広く開かれている一方で、合格するためには極めて厳しい競争を勝ち抜かなければならず、その難易度の高さは歴史上類を見ないものとして知られています。
科挙の試験内容と驚きの問題形式

moya lab イメージ
科挙の試験内容は、単なる知識の暗記だけを問うものではありませんでした。
もちろん、儒教の経典である四書五経の内容を完全に記憶していることが大前提でしたが、それに加えて高度な思考力や応用力が求められたのです。
筆記試験の構成
試験は主に筆記形式で行われ、大きく分けて以下の要素で構成されていました。
- 経義(けいぎ)・帖経(ちょうきょう): 儒教経典の一節を正確に暗記して記述したり、一部が隠された文章の全体を復元したりする問題です。記憶力の正確さが厳しく問われました。
- 詩賦(しふ): 与えられたテーマと韻に基づいて、即興で詩や賦(一種の散文詩)を作成する問題です。文学的な才能や表現力が評価されました。
- 策問(さくもん): 皇帝が提起する政治や社会に関する時事問題に対して、具体的な解決策を論述形式で回答する問題です。受験者の政策立案能力や見識が試される、最も重要な科目の一つでした。
このように、科挙では記憶力、文学的センス、そして現実的な問題解決能力という、多岐にわたる能力が総合的に評価されました。
そのため、一夜漬けのような勉強では到底太刀打ちできず、幼少期からの長期にわたる学習が不可欠だったのです。
膨大な暗記量が求められた儒教の経典

moya lab イメージ
科挙の難易度を語る上で、避けては通れないのが、その圧倒的な暗記量です。
受験生が暗記を義務付けられていたのは、儒教の基本経典である「四書五経」でした。
四書とは『大学』『中庸』『論語』『孟子』を指し、五経とは『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』を指します。
これらを合計すると、文字数はおよそ40万字から50万字にも及ぶと言われています。
現代の文庫本が1冊あたり約10万字とすると、文庫本4〜5冊分を、注釈も含めて一字一句間違えずに暗記する必要があったわけです。
しかも、ただ暗記するだけでは不十分でした。
試験では、経典の知識を前提とした論述や詩作が求められるため、内容を深く理解し、自在に応用できなければなりませんでした。
この膨大なテキストを血肉と化す作業は、多くの受験生にとって最初の、そして最大の障壁であったと考えられます。
合格率が低すぎる驚異の倍率とは
科挙の競争率、すなわち倍率は、現代のいかなる試験とも比較にならないほど過酷なものでした。
試験は複数の段階に分かれており、次の段階に進むごとに受験者がふるいにかけられていきます。
段階別の試験と合格率
科挙の主な段階と、おおよその合格率は以下の通りです。
| 試験段階 | 概要 | 合格率の目安 |
|---|---|---|
| 童試(どうし) | 最初の関門。県試、府試、院試の3段階から成り、合格すると「生員(秀才)」の資格を得る。 | 数十人に1人程度 |
| 郷試(きょうし) | 3年に1度、各省の都で行われる。合格者は「挙人」と呼ばれ、官僚になる資格を得る。 | 約100人に1人 |
| 会試(かいし) | 郷試の翌年、首都で行われる全国試験。合格者は「貢士」となる。 | 約30人に1人 |
| 殿試(でんし) | 皇帝自らが行う最終試験。順位を決めるためのもので、会試合格者は原則不合格にならない。 | – |
童試に合格するだけでも大変ですが、そこから郷試、会試と進むにつれて、倍率は天文学的な数値になっていきます。
例えば、最初の受験者から最終的に会試に合格するエリート中のエリートとなると、その割合は数千人に1人、あるいはそれ以下だったとも言われています。
この驚異的な倍率が、科挙の難しさを何よりも雄弁に物語っています。
科挙の壮絶さを示す有名なエピソード
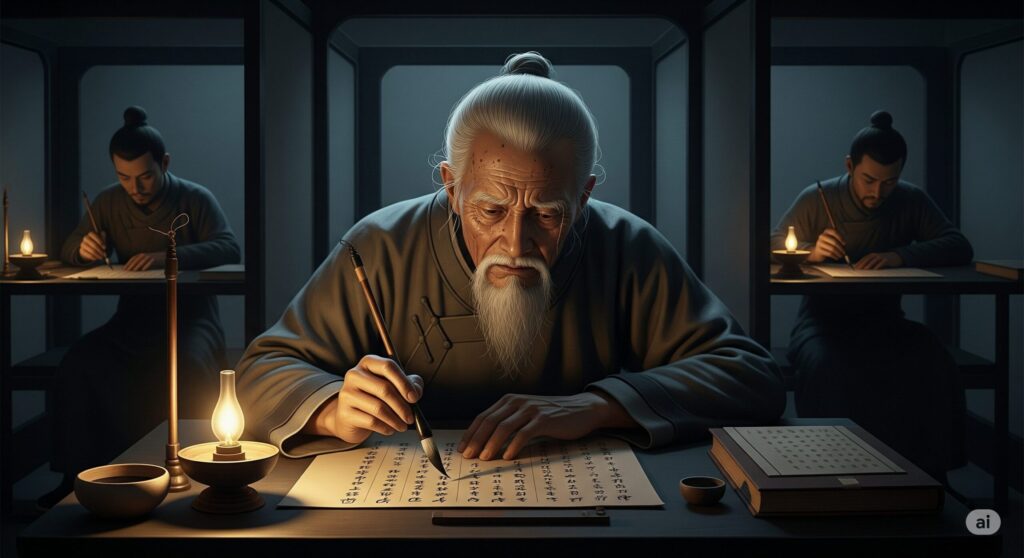
moya lab イメージ
科挙の過酷な現実は、数々の壮絶なエピソードとして後世に伝えられています。
これらの話からは、受験生たちがどれほどのプレッシャーの中で人生を賭けていたかがうかがえます。
有名なエピソードの一つに、合格するまで何十年も試験に挑み続けた高齢受験生の話があります。
中には、白髪の老人が孫のような年齢の若者たちに交じって試験を受けることも珍しくありませんでした。
80歳を超えて初めて郷試に合格したという記録や、100歳を超えてもなお挑戦を続けたという話も残っており、生涯を科挙に捧げた人々の執念を感じさせます。
また、ある受験生は、試験中に亡くなった父親の訃報を知らされ、その場で血を吐いて倒れたと言われています。
当時は親の死に際して3年間喪に服す「丁憂」という習慣があり、それは試験を諦めることを意味しました。
一族の期待と親への思いとの間で、彼の精神は限界に達したのでしょう。
これらのエピソードは、科挙が単なる試験ではなく、個人のみならず一族の運命をも左右する、人生そのものであったことを示しています。
現代と比較にならない科挙の難易度の実態
科挙の過酷さは、その試験内容や倍率だけに留まりません。
ここでは、試験の裏で横行した不正行為や、受験生を襲った精神的な苦痛、そして現代の視点から見た科挙の異常性について、さらに深く掘り下げていきます。
- 科挙で横行した驚愕のカンニング手口
- プレッシャーで発狂する受験者もいた現実
- なぜ日本に科挙がなかったのか?その理由
- 現代の国家試験とは比べ物にならないのか
- なんjでも語られる科挙のヤバい実態
科挙で横行した驚愕のカンニング手口

moya lab イメージ
これほどまでに合格が困難な試験であったため、科挙ではいつの時代もカンニング、すなわち不正行為が後を絶ちませんでした。
その手口は非常に巧妙で、現代から見ても驚くべきものが数多く存在します。
最も一般的なのは、経典の内容を極小の文字で書き写した「挟帯(きょうたい)」と呼ばれるカンニングペーパーの持ち込みでした。
米粒ほどの大きさにびっしりと文字が書かれた紙や布を、衣服の裏地や筆の軸、弁当箱の底などに隠して試験場に持ち込んだのです。
中には、カンニング専用に作られた下着まで存在したと言われています。
他にも、試験官を買収したり、替え玉受験を行ったりと、様々な不正が横行しました。
もちろん、これらの不正が発覚した場合の罰は非常に重く、永久に受験資格を剥奪されるだけでなく、厳しい拷問や処罰が待っていました。
それでもなお不正がなくならなかったという事実は、科挙に合格することがいかに大きな見返りをもたらすものであったかを物語っています。
プレッシャーで発狂する受験者もいた現実

moya lab イメージ
科挙の受験生が耐えなければならなかったのは、学問的な困難さだけではありませんでした。
精神的なプレッシャーもまた、彼らを極限まで追い詰めました。
試験は「貢院(こういん)」と呼ばれる専用の施設で、数日間にわたって泊まり込みで行われます。
受験生は一人ひとり、「号舎(ごうしゃ)」という非常に狭い個室に隔離され、食事も睡眠もその中で済ませなければなりませんでした。
この閉鎖的な空間での孤独な戦いは、精神的に大きな負担となります。
さらに、一族の期待を一身に背負い、「今回落ちたら後がない」という絶望的な状況に置かれた受験生も少なくありませんでした。
何度も落第を繰り返すうちに精神の均衡を失い、試験中に突然大声で叫びだしたり、奇行に走ったりして「発狂」する者もいたと記録されています。
これらの悲劇は、科挙という制度が持つ、人の人生を大きく狂わせるほどの負の側面を浮き彫りにしています。
なぜ日本に科挙がなかったのか?その理由

moya lab イメージ
中国でこれほど長く続いた科挙制度ですが、隣国である日本では本格的に導入されることはありませんでした。
これには、日本の歴史的・社会的な背景が深く関係しています。
奈良時代や平安時代、日本は遣唐使などを通じて中国(唐)の進んだ制度や文化を積極的に取り入れており、科挙制度についても知識はありました。
しかし、当時の日本は藤原氏をはじめとする有力な貴族が政治の中枢を握る「氏族社会」でした。
官職は能力よりも家柄で決まることが多く、有力貴族の子弟は教育を受ければ無試験で官僚になれる制度(蔭位の制)があったのです。
能力主義である科挙の導入は、こうした貴族たちの既得権益を脅かすものであり、強い抵抗があったと考えられます。
菅原道真のように、能力を重んじる立場から科挙の導入に近い提案をした人物もいましたが、結局は定着しませんでした。
その後、武士が力を持つ時代になると、政治はますます家柄や主従関係が重視されるようになり、科挙のような試験制度が入り込む余地はなくなっていきました。
現代の国家試験とは比べ物にならないのか
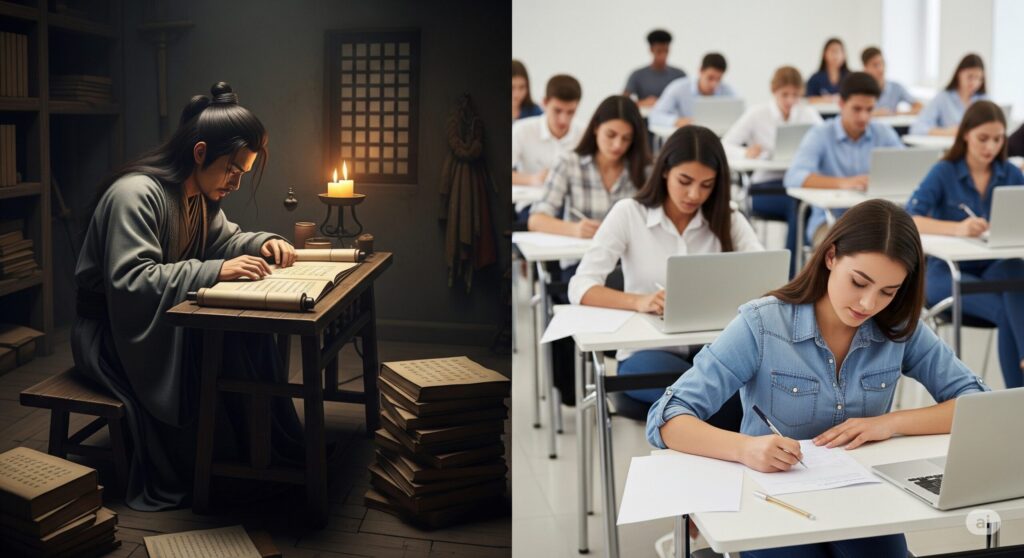
moya lab イメージ
現代にも、司法試験や医師国家試験、公務員採用試験など、難関とされる試験は数多く存在します。
しかし、これらの試験と科挙を比較すると、その性質や過酷さには大きな違いが見られます。
| 比較項目 | 科挙 | 現代の主な国家試験 |
|---|---|---|
| 試験期間 | 数日~1週間以上に及ぶ泊まり込み | 1日~数日程度(泊まり込みは稀) |
| 学習範囲 | 四書五経を中心とした膨大な古典。範囲は限定的だが深い理解と応用力が必須。 | 法律、医学、行政など専門分野が多岐にわたり、常に情報が更新される。 |
| 合格後の地位 | 国家のエリート官僚として絶大な権力と名誉を得る。社会的身分が激変する。 | 専門職としての資格を得る。社会的地位は高いが、科挙ほどの身分変動はない。 |
| 受験期間 | 年齢制限がなく、生涯をかけて受験する者も多い。 | 受験回数や年齢に制限がある場合が多い。 |
| 精神的負担 | 閉鎖空間での長期戦、一族の期待など、極めて高いプレッシャー。 | 高いプレッシャーはあるが、科挙ほどの極限状況は少ない。 |
もちろん、現代の試験が簡単だというわけではありません。
しかし、人生の全てを賭け、合格すれば一族郎党の運命が変わり、落ちれば全てを失うという科挙のシステムは、現代の尺度では測れないほどの異常なプレッシャーと過酷さを持っていたと言えるでしょう。
なんjでも語られる科挙のヤバい実態

moya lab イメージ
科挙の異常なまでの過酷さは、インターネットが普及した現代においても、たびたび話題に上ります。
特に、匿名掲示板である「なんj(なんでも実況J)」などでは、その「ヤバい」実態が面白おかしく、あるいは畏怖の念をもって語られることがあります。
スレッドでは、「現代の試験で例えるなら何?」「もし自分が受けたら初日で発狂する」といった書き込みが見られ、多くの人が科挙を歴史上の単なる出来事としてではなく、現代人の感覚から見ても異常な制度だと捉えていることがわかります。
カンニングの手口や発狂する受験生のエピソードは特に人気が高く、「昔の人の執念はすごい」「人生を賭けた無理ゲー」といった感想が寄せられます。
このように、ネット上で語られることで、科挙は歴史に詳しくない人々にもその特異性が伝わり、時代を超えて人々の興味を引きつけているのです。
改めて振り返る科挙の難易度の高さを総括
この記事では、科挙の難易度について多角的に解説してきました。
最後に、本記事の要点を以下にまとめます。
- 科挙は家柄を問わず官僚になれる画期的な登用試験制度だった
- 合格は本人だけでなく一族全体に絶大な名誉と富をもたらした
- 試験内容は四書五経の完全な暗記が前提とされた
- 暗記だけでなく詩作や政策論述など応用力も問われた
- 暗記量は現代の文庫本で4〜5冊分にも及んだ
- 試験は複数の段階に分かれ最終的な合格率は数千分の一以下だった
- 何十年も受験し続ける高齢の受験生は珍しくなかった
- あまりの難しさから巧妙なカンニングが横行した
- 発覚した場合の罰は非常に重かった
- 閉鎖空間での試験は受験生に極度の精神的負担を強いた
- プレッシャーから精神に異常をきたす者もいた
- 日本では貴族社会の構造から科挙は定着しなかった
- 現代の国家試験と比較してもその過酷さは群を抜いている
- 生涯を賭けて挑む点や合格後の身分の変化が現代とは大きく異なる
- ネットの掲示板でもその異常な難易度がたびたび話題になる








